NEW

電気自動車(EV)の税金はいくら?減税措置や補助金も紹介
公開日:2024/01/31更新日:2024/05/13
目次
電気自動車(EV)を購入時にかかる税金
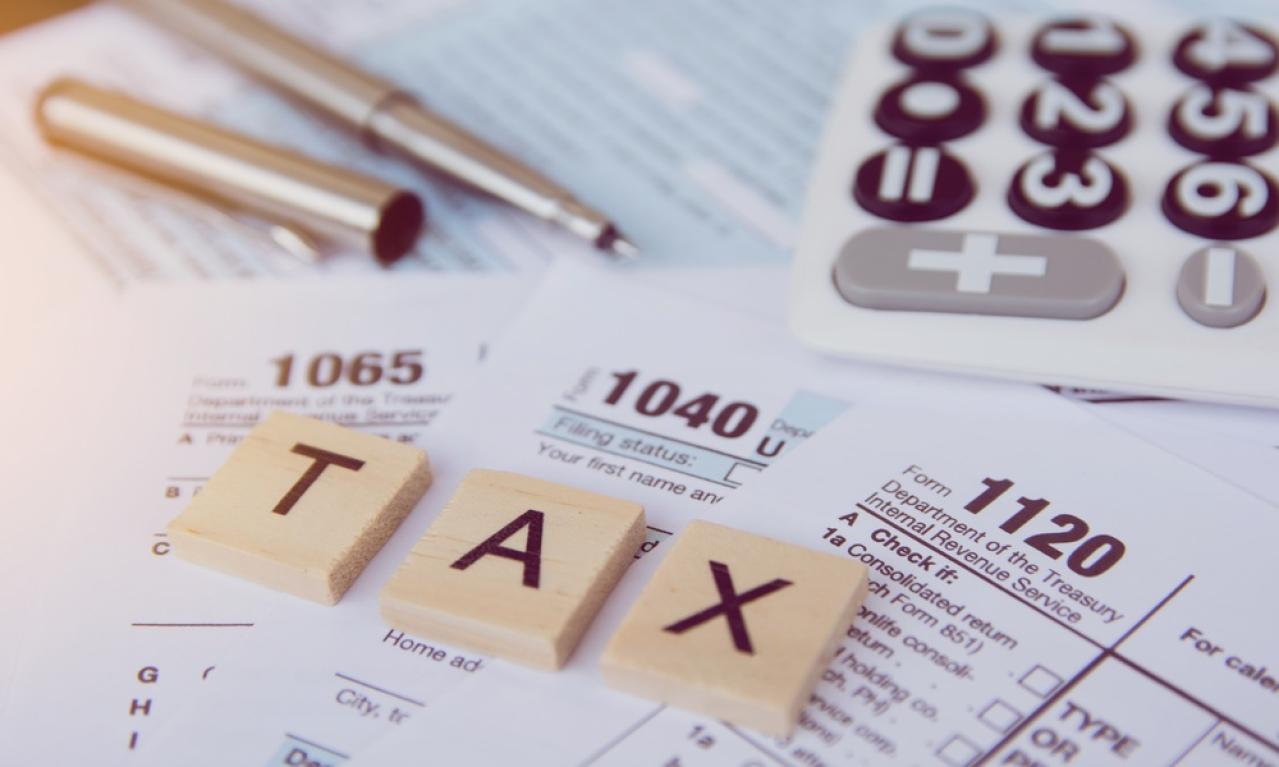
電気自動車(EV)を購入する際にかかる税金について以下の項目で解説します。電気自動車を購入する際には、「自動車税(種別割)」と「自動車重量税」、そして消費税がかかります。それぞれの内容をさらに詳しくみていきましょう。
電気自動車の自動車税(自動車税種別割)
電気自動車の自動車税(自動車税種別割)とは、車の使用用途や総排気量によって定められる車の税金です。原則、毎年4月1日時点で車を所有する方に課税される税金であり、年税額を一括で納付する仕組みになっています。排気量ごとに負担する自動車税について、分かりやすく以下の表にまとめました。
| 総排気量 | 2019年10月1日以降に 新規登録した車の税額 | 2019年9月30日以前に 新規登録した車の税額 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 2万5,000円 | 2万9,500円 |
| 1,000〜1,500cc | 3万500円 | 3万4,500円 |
| 1,500〜2,000cc | 3万6,000円 | 3万9,500円 |
| 2,000〜2,500cc | 4万3,500円 | 4万5,000円 |
| 2,500〜3,000cc | 5万円 | 5万1,000円 |
電気自動車は、ガソリンを使用しないため、「1,000cc以下扱い」となります。そのため、2019年10月1日以降に新規登録した車の場合、「2万5,000円」、2019年9月30日以前に新規登録した車は「2万9,500円」です。
仮に年度内で6月に電気自動車を新規登録した場合、6月〜3月分までの自動車税を支払う仕組みになります。自動車税額は、100円未満が切り捨てされます。
電気自動車の自動車重量税
自動車重量税とは、車種ごとの車両重量に応じて課税される国税です。自動車重量税は、新規登録と継続検査(車検)のタイミングで納付する義務が発生します。車両重量ごとに負担する重量税を分かりやすく以下の表にまとめました。
| 車両重量 | 新規登録時(3年分) | 継続検査時(2年分) |
|---|---|---|
| 500kg以下 | 1万2,300円 | 8,200円 |
| 1,000〜1,500kg | 2万4,600円 | 1万6,400円 |
| 1,500〜2,000kg | 3万6,900円 | 2万4,600円 |
| 2,000〜2,500kg | 4万9,200円 | 3万2,800円 |
| 2,500〜3,000kg | 6万1,500円 | 4万1,000円 |
| 3,000kg〜 | 7万3,800円 | 4万9,200円 |
自動車重量税は、0.5tごとに4,100円課税される計算です。仮に1,000kgの車に課税される自動車重量税を新規登録時に3年分納める場合、2万4,600円の重量税が必要になります。電気自動車の車両重量を把握した上で、自分にとって最適な車を購入検討しましょう。
電気自動車は環境性能割が非課税
自動車税(環境性能割)は、車の燃費性能や車の取得時に発生する税金です。課税される環境性能割は、自家用車の場合、車の取得金額の1〜3%程です。
ガソリン車の場合、環境性能割が課税されますが、電気自動車の場合には環境性能割が非課税となります。
電気自動車(EV)で受けられる税制優遇措置

電気自動車(EV)で受けられる税制優遇措置を詳しく解説します。具体的に紹介する税制優遇措置は以下の通りです
- グリーン化特例
- エコカー減税
- 環境性能割
グリーン化特例
グリーン化特例とは、購入する電気自動車の排出ガス性能や燃費性能に合わせて、新車登録年度と翌年度の自動車税を軽減する税制優遇措置です。グリーン化特例が適用された電気自動車の場合、2万5,000円の自動車税が75%軽減されることで、6,500円の税負担になります。
グリーン化特例は当初2023年3月31日までの限定措置として適用されていましたが、適用期間が延長されたことで2023年4月1日〜2026年3月31日までに新しく設定されました。グリーン化特例が適用される車種は、普通車以外に軽自動車でも適用される税制優遇措置です。
エコカー減税
エコカー減税とは、排出ガス性能と燃費性能に優れた車の自動車重量税を免税・軽減する税制優遇措置です。エコカー減税もグリーン化特例と同じく、2023年4月末までの特例措置でしたが、物価高や半導体不足による新車の納期遅れの影響もあり、電気自動車に関して2026年4月30日の新規登録分まで軽減制度が適用されます。
エコカー減税では、購入時の新規車検分と継続車検分の自動車重量税が免税になる優遇制度です。実際にエコカー減税が適用されているタイミングを狙い、新車として電気自動車を購入する方が意外に多いのが現状です。
環境性能割が非課税
電気自動車は環境性能割の非課税対象として設定されています。しかし、非課税期間が永久的ではありません。2026年3月31日まで非課税期間が続くことが表明されており、2026年3月31日以降は、環境性能割が改定される可能性も考えられます。
電気自動車(EV)を購入時に受けられる補助金

電気自動車(EV)を購入する際に受けられる補助金を詳しく解説します。具体的な補助金については以下の通りです。
- クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)
- 地方自治体の補助金
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)とは、プラグインハイブリッド車や燃料電池自動車、電気自動車の導入を支援するための補助金です。国内では2050年のカーボンニュートラルに向けて電気自動車やプラグインハイブリッド車などの普及を急速に進めています。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の補助対象は、2024年2月2日以降に新車新規登録された普通車や軽自動車です。補助金として交付される金額は交付対象となる車両の車種や登録日、申請する都道府県によって異なります。
補助金の上限額も決まっており、上限額を超えた場合、補助金制度は終了してしまうため、早い段階で電気自動車の購入を検討する必要があるでしょう。具体的に適用される補助金額を以下の表で分かりやすくまとめました。
| 適用車種 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 85万円 |
| プラグインハイブリッド車 | 55万円 |
| 燃料電池自動車 | 255万円 |
地方自治体の補助金
電気自動車の購入に関しては、国の補助金以外に地方自治体からも補助金が出ます。ただし、交付される補助金は地方自治体ごとに上限金額や交付される条件が異なり、全ての地方自治体が電気自動車に対する補助金を交付している訳ではありません。
東京都の場合、「ZEV補助金」を申請可能であり、助成対象は電気自動車とPHEV、FCV車両です。交付される補助金額について以下の表でまとめました。
| 適用車種 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 35万〜45万円 |
| プラグインハイブリッド車 | 35万〜45万円 |
| 燃料電池自動車 | 100万〜110万円 |
地方自治体の補助金を利用したい場合には、まず現在お住まいの自治体が電気自動車に関する補助金を交付しているのかを自治体の公式ホームページで確認する必要があります。
電気自動車(EV)を購入後にかかる税金

電気自動車(EV)を購入した後にかかる税金を詳しく解説します。下記内容では、電気自動車を購入後にかかる具体的な税額以外に納付タイミングも解説しています。それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
電気自動車を購入後にかかる税金
電気自動車を購入した場合、「自動車税(種別税)」と「自動車重量税」「消費税」の3種類の税金がかかります。ガソリン車を購入した場合、車を取得する際に発生する環境性能割を購入者が負担する必要がありますが、電気自動車の場合、非課税です。
電気自動車は、ガソリンを使用しない車のため、1,000cc以下の扱いとなり、負担する自動車税額は2万5,000円です。納付時期は毎年5月頃の予定です。
自動車重量税は、電気自動車の車両重量によって異なります。基本的には、0.5tごとに4,100円課税される金額が増える仕組みになっています。
購入後5年目までにかかる税金をシミュレーション
電気自動車を購入後5年目にかかる税金をシミュレーションしてみました。以下の表は、車両総重量1t未満で初度登録から5年目の車両を条件に算出しています。
| 税金項目 | 納付税額 |
|---|---|
| 自動車税 | 2万5,000〜2万9,500円 |
| 自動車重量税 | 1万6,400円 |
| 合計 | 4万1,400〜4万5,900円 |
電気自動車の場合「自動車税」と「自動車重量税」の2つの税金負担が発生します。自動車税については、2019円10月1日以降に新規登録している車の場合には、「2万5,000円」、2019年9月30日以前に新規登録している場合には、「2万9,500円」の税負担が発生するでしょう。
自動車重量税は、新規登録と継続車検のタイミングで課税が義務付けされています。今回の重量税金額は電気自動車を購入後、5年目の条件であるため、継続検査(2年分)の重量税が課税される仕組みです。5年目に課税される電気自動車の税負担を理解しつつ、車の維持費を把握していくことをおすすめします。
電気自動車とガソリン車の税金を比較
電気自動車とガソリン車の税金を「自動車税」と「自動車重量税」の2つに分け、以下の表で分かりやすく比較してみました。
【自動車税】
| 総排気量 | 電気自動車 | ガソリン車 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 2万5,000円 | 2万5,000〜2万9,500円 |
| 1,000〜1,500cc | 2万5,000円 | 3万500〜3万4,500円 |
| 1,500〜2,000cc | 2万5,000円 | 3万6,000〜3万9,500円 |
| 2,000〜2,500cc | 2万5,000円 | 4万3,500〜4万5,000円 |
| 2,500〜3,000cc | 2万5,000円 | 5万〜5万1,000円 |
【自動車重量税】
| 車両重量 | 新規登録時(3年分) | 継続検査時(2年分) |
|---|---|---|
| 500kg以下 | 1万2,300円 | 8,200円 |
| 1,000〜1,500kg | 2万4,600円 | 1万6,400円 |
| 1,500〜2,000kg | 3万6,900円 | 2万4,600円 |
| 2,000〜2,500kg | 4万9,200円 | 3万2,800円 |
| 2,500〜3,000kg | 6万1,500円 | 4万1,000円 |
| 3,000kg~ | 7万3,800円 | 4万9,200円 |
電気自動車の場合、ガソリンを使用することがないため、排気量は1,000cc以下として設定されます。そのため、負担する自動車税は2万5,000円です。重量税は車両総重量によって異なりますが、エコカー減税が適用される場合、ガソリン車よりも減税された自動車重量税で一定期間負担する税金を減らせるでしょう。
電気自動車(EV)の税金以外にかかる主な維持費

電気自動車の税金以外にかかる維持費はメンテナンス費用と充電費用、バッテリー交換費用が挙げられます。とくに充電費用は急速充電と普通充電で負担する充電費用が異なるため、それぞれの費用を比較した上でどちらの方法で充電するのか判断しましょう。
また、電気自動車には、バッテリーが搭載されています。バッテリー容量によってメーカー保証期間が異なりますが、目安は8年16万kmを想定しておきましょう。バッテリー交換時にも交換費用が発生します。具体的な交換費用として、5万円〜10万円ほどの負担が必要になります。メンテナンス料金は、期間や業者によって異なるため、それぞれのメンテナンス業者で費用を比較することが重要です。
電気自動車(EV)の税制優遇措置はいつまで?期限はある?

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の補助対象は、2024年2月2日以降に新車新規登録された普通車や軽自動車です。補助金として交付される金額は交付対象となる車両の車種や登録日、申請する都道府県によって異なります。
エコカー減税もグリーン化特例と同じく、2023年4月末までの特例措置ですが、物価高や半導体不足による新車の納期遅れの影響もあり、2026年4月30日の新規登録分まで軽減制度が適用される制度です。
電気自動車(EV)の税金は税制優遇・補助金でお得に!
電気自動車の車両購入価格は、ガソリン車やハイブリッド車以上に高い価格で設定されています。「高すぎる」というマイナス要素を感じる方も中にはいますが、電気自動車を購入する際に適用される税制優遇制度や補助金を活用することで、お得な条件で希望車種を購入できるでしょう。
補助金は交付される上限金額や交付期間が限定されています。この記事の内容を参考にして、お得な税制優遇制度や補助金を活用しつつ、電気自動車を購入してみてください。
こちらもオススメ
こちらもオススメ





