NEW
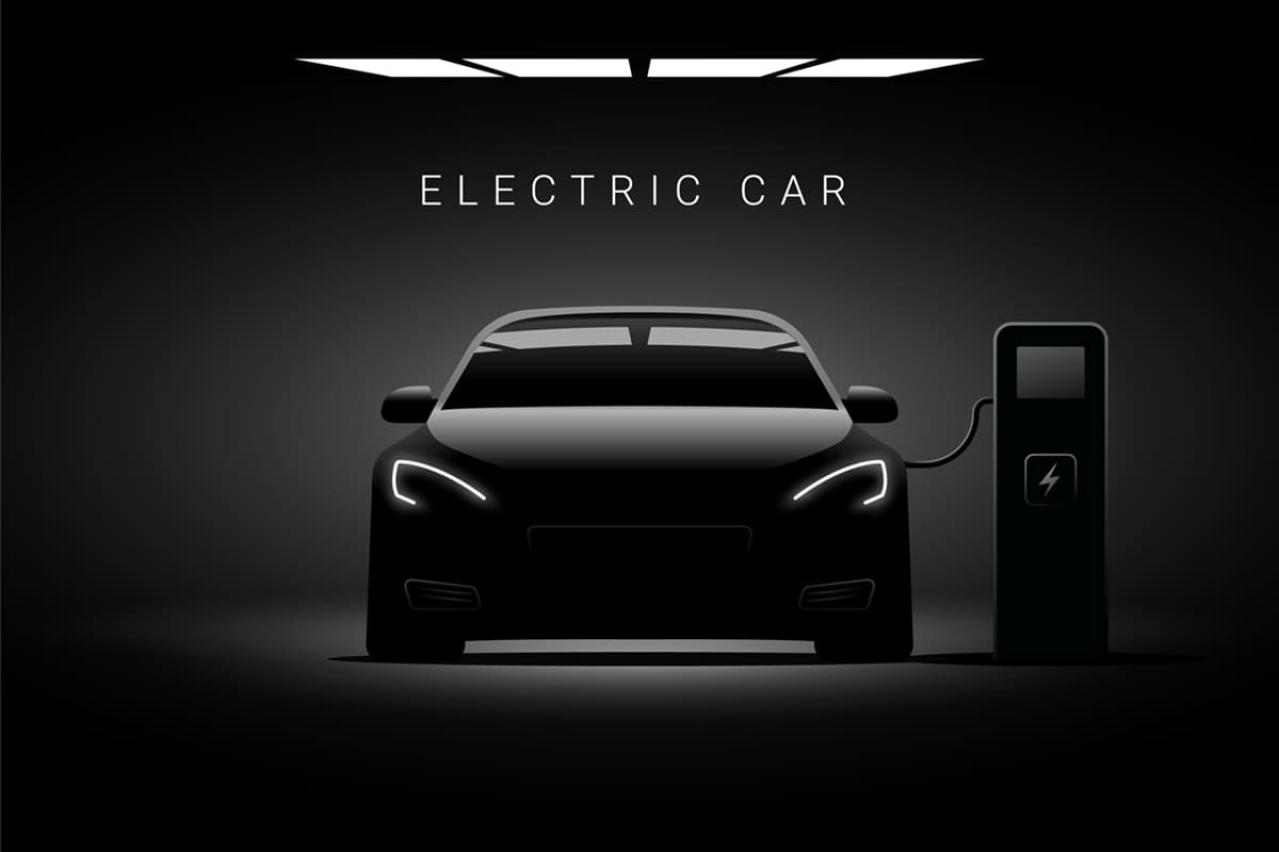
歴史は繰り返す?!今のBEVと同じように否定されていたHEVが受け入れられるまで(3)
公開日:2024/08/15更新日:2024/08/15
目次
HEVの普及と同時に、BEVも一般的になっていったあの頃

世間一般ではHEVが「まだまだ高価で無駄が多い、あるいは贅沢な乗り物」だった1990年代後半から2000年代にかけ、BEVも実験的で高額なリース販売がメインとはいえ、バッテリーやモーターの高性能化が進みました。
そもそもHEVにせよBEVにせよ、「いかにバッテリーをうまく使い、モーターで効率よく走るかが、性能へ大きく影響を与える」という部分は共通しており、HEVのために開発した技術でBEVも大きく進展したり、あるいは同じ問題を抱えていたものです。
大々的な宣伝で世に知られるようになったBEVは三菱のi-MiEV(2009年)からなので、HEVとは異なり自動車メディアでも熱心なコラムニストや評論家が細々と伝える程度だった、「HEVと並行で発展していた時期のBEV」を、以下で紹介してみましょう。
技術的には「HEVの応用」という部分も多いのですが、2020年代になってようやく注目を浴びるコンセプトが、20年ほど早く登場しており、自動車メーカー各社がHEVの普及へ悪戦苦闘していた中、早くも「HEVの次」を目指していたことがわかります。
つまり「いずれ普及するもの」という予測が登場時には既にあったからこそ、HEVは市販されたのであり、HEV化が困難なジャンルは代替技術の次(BEV)も早く準備せねばならず…と、メーカー側の「時間の流れ」は、ユーザーより早く流れていたのです。
日産 プレーリージョイEV(1997年)
トヨタから世界初の本格量販HEV(ハイブリッドカー)、初代「プリウス」が発売された1997年、日産から30台をリース販売したのがプレーリージョイEVです。
ベースになったのは1988年にFF乗用車ベースのロールーフミニバン「プレーリー」として発売後、しばらくはパッとしなかったものの、ミニバンやSUVが次々に大ヒットして市民権を得ていった「RVブーム」に乗る形で1995年にビッグマイナーチェンジ。
プレーリージョイと車名も改め再出発し、1998年まで販売される間の末期に登場したBEV版なので、車としての基本設計は相当に古かったのですが、搭載されたのはソニーと共同開発していた、なんと世界初の自動車用リチウムイオンバッテリー!
最高速120km/h、航続距離は10・15モードで200km以上…WLTCモード換算ならわずか126km程度ではありましたが、リース専用の少数販売車とはいえ、今から27年も前にリチウムイオンバッテリーの実用車が存在したことに驚きです。
しかも2000年には北欧のノルウェーでもさらに北極圏、スピッツベルゲン島の国立極地研究所北極観測センターに配備され、「冬には航続距離が激減するはずのBEV」であるにも関わらず、酷寒の環境下で6年も無故障で稼働を続けています。
プリウス誕生の年は、リチウムイオンバッテリーBEV誕生の年でもありました。
ホンダ EV Plus(1997年)
プリウスが発売された1997年はホンダにとっても記念すべき年で、リース販売とはいえホンダ初のBEV「EV Plus」が発売されました。
他のメーカーは戦中・戦後のガソリン不足な時期や、その後も1970年の大阪万博などに合わせて鉛バッテリーのBEVを開発していましたが、4輪車の主要メーカーとして最後発だったホンダはなかなか余裕がなく、1988年にようやく研究開発がスタート。
最初はわずか4人のメンバーでCR-Xをベースに改造EVを走らせ、1991年には百数十人規模へ拡大してシビックがベースの改造EVを走らせますが、いずれも「市販車にとにかくバッテリーをたくさん積んで、モーターで走らせただけ」というレベル。
そこから普通に市販できるBEVを開発するのは大変でしたが、当時はアメリカのカリフォルニア州やヨーロッパでも排ガスを全く出さない「ZEV」へつながる法律や規制が始まっており、将来を考えれば本腰を入れるしかありません。
モーターやインバーター(制御装置)はホンダらしく内製化し、環境の変化に弱い鉛バッテリーに代わるニッケル水素バッテリーはバッテリーメーカーと共同開発します。
ボディはコンパクトカーのロゴ(1996年)と似ていましたが、BEV専用で新規に起こされたデザインで、航続距離は10・15モード220km。
世界各国で少数ずつ、合計300台限定のリース販売でしたが、EV Plusのために開発されたDCブラシレスモーターやニッケル水素バッテリーは、1999年に発売されたホンダ初のHEV、初代インサイトにも採用されており、BEVからのスピンオフでHEVも作れた形です。
その後のホンダは各種HEVのほか、FCEV(燃料電池車)やBEVを並行開発し、2010年代後半に販売していたクラリティではFCEV、PHEV(プラグインハイブリッド)、BEV(日本未発売)の3種類を1車種で販売し、2020年には初の通常市販BEV、ホンダeを発売。
2024年にはプラグインFCEVのCR-V e:FCEVや、軽商用BEVのN-VAN e:を発売し、日本で唯一「2040年に内燃機関(エンジン)の廃止」を明言するなど、今やBEVやFCEVの最先端メーカーになろうとしています。
日産 ハイパーミニ(2000年)
プレーリージョイEVやルネッサEV(1998年)でリチウムイオンバッテリーBEVの経験を積んだ日産が、市販BEVとしては同社初の専用ボディで2000年に発売したのが2人乗りマイクロカー(軽乗用車)が、ハイパーミニです。
小さいながらリアハッチを持つ実用的な3ドアハッチバック車で、リチウムイオンバッテリーの容量はわずか8.1kWh、10・15モード航続距離も約115kmと短いものの、最高速度100km/hで高速道路も走れて、現在の2シーター超小型モビリティより走行性能は充実。
通常の購入も可能ですが400万円とかなり高額、軽自動車でも上級グレードなら200万円台が珍しくない2020年代と異なり、当時の主力車種、スズキ ワゴンRの最上級モデルでも153万円程度という時代の400万円です。
ガソリン代が安くてHEVですら割高という頃ですから、いくら電気代が安くとも2シーターのシティコミューターとしては高すぎましたが、日本で初めて改造車扱いではなく型式指定(EA0型)を取って市販されたBEVとして、歴史に残っています。
アラコ エブリデーコムス(2000年)
2024年現在も販売が続けられている、トヨタのミニカー「コムス」(2012年)の初代にあたる2000年発売のミニカーBEVがエブリデーコムスで、コムスを生産するトヨタ車体の前身、旧「アラコ」で開発・生産されて、トヨタ店やカローラ店でも販売されました。
ミニカー規格のBEV自体はダイハツ(ミニスウェイ・1995年)、タケオカ自動車工芸(EV1ルーキー・1997年/ミリュー/MC-1 EV・1999年)などが販売されていたものの、トヨタでも一般販売した公道向けBEVとしては史上初。
しかも左右後輪にインホイールモーターを仕込み、カーブを曲がる時には回転数制御すら行うという、ある意味では現行コムスより先進的な設計でしたが、もっとも価格に影響する電池が普通の鉛バッテリーなので、発売時の価格も68.5万〜75.5万円と手頃です。
1人乗りで航続距離55km、最高速度も50km/hと、公道で普通に走るには満足いく性能とは言いがたかったものの、初代プリウスを販売していたトヨタ店ではHEV(プリウス)もBEV(エブリデーコムス)も買えるという、当時としては珍しい販売状況でした。
発売から2代24年かかって、最近では地方都市でも業務用に使われる姿をよく見かけるようになり、中古車も手頃な価格でそれなりのタマ数が揃い、ドアをつけたりリチウムイオンバッテリーに換装するカスタマイズも見られますが、このエブリデーコムスが原点です。
三菱 i-MiEV(2009年)
1996年に世界初の量産車用直噴エンジン「GDI」を発表するなど、環境性能と動力性能の両立に熱心だった三菱ですが、電動化に関しては他社と異なりHEVにはあまり手をつけず、2006年に軽BEVの「i-MiEV」を発表して、世間をアッと言わせました。
そもそも三菱は1990年代にRVブームで絶好調だったのが、2000年代に入って早々に相次いだスキャンダルで一気にイメージダウン、しかし地道に商品改良や新型車の開発を続け、2006年にはミッドシップ後輪駆動の斬新な新型軽乗用車「i(アイ)」を発売。
この「i」のリア床下エンジンをモーターへ換装し、フロア床下へ走行用バッテリーを敷き詰めたのがi-MiEVで、もともと時代を超越したような近未来的なプロポーションへ、現在でも通用しそうな…むしろ今発売しても最先端と言われそうなBEVを作ってしまいました。
もっとも、2009年7月の法人向け発売を経て2010年4月に発売された時の価格は398万円、容量16kWhのリチウムイオンバッテリーを積んで10・15モード航続距離160km(WLTCモード換算で約100km程度)と、当時の技術ではやはり「まだ高価で性能不足」ではあります。
特に2009年にはトヨタから3代目(30系)プリウスが発売、ようやく信頼性が確立されて市場にも定着していたところへ、性能も実用性も、価格も満足いくモデルが登場したということでHEV史上に残る大ヒットとなり、i-MiEVの存在はかすみがちでした。
しかし「軽自動車でこれだけの性能をこの価格、リースではなく普通に安く買えて、CEV補助金(1998年からあった)も出る」のは画期的で、同年発売の初代日産 リーフとともに、初めてBEVを買おうと思った、そして実際に買ったユーザーが数多くいたのです。
2021年には販売を終えたものの、今も中古BEVの定番車種として手頃な価格で手に入るため「電気自動車のお試し」には適しており、10.5kWhと容量は小さいながらも劣化しにくい東芝SCiBを積む、「M」グレードもあります。
HEVとは違う意味での「普通の車」を目指さねばならないBEV

3代目(30系)プリウスの大ヒットでHEVの普及が急速に進んだ2010年代、BEVもi-MiEVや初代日産 リーフの登場で少しずつ市民権を得ていっており、HEVがすっかり「普通の車」になった2020年代の今は、BEVが初期のHEVにあたるポジションにあります。
ただしHEVが結局は「給油するという意味では純エンジン車と同じ」で、「燃費がよくてあまり給油しなくていい便利な車」として、それまでの「普通の車」からは延長線上にあったことで、普及しても困ることはありませんでした。
しかしBEVはそもそも「自宅や拠点で充電が基本であり、それが無理な場合や足りない場合は出先で充電」と、純エンジン車はもちろん、その延長線上であるHEVとは「普通の使い方」が大きく異なります。
BEVそのものの技術はHEVの延長線上にあっても、普及にいっそう高いハードルを感じさせるのはこのためで、「HEVが普通になったんだから、BEVも同じように」とはなかなかいきません。
それでも自宅や駐車場など拠点での充電で間に合う範囲なら、ガソリンスタンドへ行くような感覚で充電スポットへ行く必要すらない、というBEVのメリットが理解され、いつの間にか「当たり前に」になった時、かつてのHEVのように「高いだけの無駄な乗り物」から「普通の車」へならないと、誰が断言できるでしょうか?
このブランドについて
-

NISSAN
日産
かつては日本第2位の自動車メーカーであり、自他ともに求める「技術の日産」として、真剣なクルマ選びに値する玄人好みのクルマがユーザーに支持される日産自動車。フェアレディZやスカイライン、GT-Rといった歴史と伝統を誇るV6DOHCターボエンジンのハイパワースポーツをイメージリーダーとして大事にする一方、2010年に発売したリーフ以降、SUVのアリア、軽自動車のサクラなど先進的なBEVをラインナップ。さらにエンジンを発電機として充電いらず、従来どおり燃料の給油で乗れる「e-POWER」搭載車を増やしており、モーターのみで走行するクルマの販売実績では、日本No.1の実績を誇るメーカーでもあります。
yu_photo - stock.adobe.com
このブランドについて
-

HONDA
ホンダ
現存する日本の主要自動車メーカーでは1960年代に最後発で四輪へ進出、大手の傘下に入ることもなく独立独歩で成長したホンダ。初期のスポーツカー「S」シリーズやF1参戦でスポーツイメージが強い一方、初代シビックの成功や、可変バルブ機構を採用した高性能なVTECエンジンで実用的かつスポーティな大衆車メーカーとして発展、1990年代にはミニバンのオデッセイやステップワゴン、SUVのCR-Vをヒットさせ、2010年代には軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」の大成功で軽自動車ブームの中心になっています。先進技術の開発にも熱心で、ハイブリッドカーやBEVなど電動化、運転支援システムの実用化にも積極的。
このブランドについて
-

MITSUBISHI
三菱
近年の三菱自動車は、ミニバン型のデリカD:5、軽スーパーハイトワゴンのデリカミニ、ピックアップトラックのトライトンに正統派のアウトランダーと、ラインナップのほとんどをSUVが占め、長年培った電子制御技術によって、AWDでも2WDでも優れた走行性能を発揮するのが特徴。軽BEVのeKクロスEVやミニキャブMiEV、アウトランダーやエクリプスクロスではPHEVタイプのSUVも好評で、規模は小さいながらもSUVや商用車の電動化では最先端を走るメーカーです。日本でのイメージリーダーは「デリカ一族」のデリカD:5とデリカミニですが、日本でも人気が再燃したピックアップトラック市場へトライトンを投入します。
著者プロフィール



