NEW

EVをより普及させるために考えたいさまざまな課題
公開日:2024/03/12更新日:2024/02/28
本記事では、EVの普及に向けて直面しているさまざまな課題を深掘りして考察していきます。
目次

カースモーラちゃんのPICK UP
- 価格やバッテリーの問題など、まだまだEV普及には課題がありそうだね。
- インフラを整えるための政策や規制の整備も不可欠だね。
課題1:やや高めな車両価格

EVはガソリン車と比較すると高価格な傾向にありますが、EV普及のためには価格の問題は避けて通れません。この章ではEVの車両価格について解説していきます。
車両価格に影響を及ぼすバッテリー価格
ガソリン車と比較するとEVはやや高価格ですが、主な理由はEVのバッテリーが高コストであることが挙げられます。それはEVのメインバッテリーである、リチウムイオンバッテリーの製造に必要な原材料の価格が高いことが原因の一つ。
このバッテリーにはコバルトなど高価なレアアースが使用されており、それが生産コストの上昇に繋がっています。これらの原材料の生産国は海外に集中しており、日本では輸入に依存する状況です。
バッテリーのコストはEVの価格に大きく影響を及ぼすため、バッテリーそのものの小型化や製造コスト削減はEVの価格低下に寄与する可能性があります。バッテリー技術の開発は国際的に競争が激しくなっており、高品質で低価格なバッテリーの開発も期待されています。
EVの普及が進めば、大量生産による材料コストの削減が可能になり、市場競争や円相場の安定などによってEVの価格が徐々に低下するかもしれません。
従来のガソリン車と比較するとどれぐらい価格が違うの?
日本国内において、国産EVの価格はおおよそ300万円から600万円の範囲にありますが、ガソリン車は一般的に100万円から300万円程度で購入可能です。
この価格の差異は、前述したように高価なリチウムイオンバッテリーを搭載することに由来しています。しかし、総合的なコストを考慮すると、EVの方が経済的であることも。
政府や自治体からの補助金の提供があること、ガソリン給油に比べて充電費用が安いことなどが、EVのランニングコストを低く抑える要因となっています。
このような要素を踏まえると、EVは初期投資は高いものの、長期的にはコスト効率が良い選択肢となる可能性があります。
補助金を使えば購入費用が安くなる?
EVの車両価格は普及の障壁となることがありますが、国や自治体の補助金を活用することでこの価格差は大幅に縮まる可能性も。例えば、国が実施している令和4年度のCEV補助金を利用すると、車両価格に大きな変動が見られます。
車種 | メーカー | 車両価格 | R4年度 CEV補助金 | R4年度補助金 適用後価格 |
eKクロスEV | 三菱自動車 | 239.8万円~ | 55万円 | 184.8万円~ |
SAKURA | 日産自動車 | 254.9万円~ | 55万円 | 199.9万円~ |
LEAF | 日産自動車 | 408.1万円~ | 78.6万円 | 329.5万円~ |
MX-30 EV | マツダ | 451万円~ | 51.6万円 | 399.4万円~ |
Honda e | 本田技研工業 | 495万円~ | 71.1万円 | 423.9万円~ |
アリア | 日産自動車 | 539万円~ | 92万円 | 447万円~ |
レクサス UX 300e | 日産自動車 | 580万円~ | 85万円 | 495万円~ |
ソルテラ | SUBARU | 594万円~ | 85万円 | 509万円~ |
※車両価格は各メーカーHPから引用、補助金交付額に関しては次世代自動車振興センターの対象車両一覧より引用(2023年1月12日時点)
この補助金を利用することで、EVの購入価格が「ガソリン車と同等」または「ガソリン車より少し高い」程度に抑えられるかもしれません。具体的な補助金の額や条件は、予算の配分や個々の車両の仕様によって異なるため、購入を検討する際には、最新の情報を確認してください。
課題2:電力不足で走行できなくなる可能性

航続距離が比較的短いEVは、電気が使用できない「電欠状態」に陥ると充電不足になってしまい、走行ができなくなるリスクがあります。計画不足による充電不足や、予期せぬ渋滞などが原因となることが電欠状態に繋がる要因と言えるでしょう。
EVはモーターで駆動するため、バッテリーの電気残量がなくなれば動けなくなってしまいます。これはエンジン車のガス欠に似ています。
そのため、バッテリーの残量管理と適切な充電計画はEVを運転する上で非常に重要です。JAFによると、2020年度のEVのロードサービス件数の約10%が電欠によるものだったようです。
2022年においてはEVの電欠事故は700件を超え、増加傾向にあると報告されています。
電欠状態になったらどうすれば良いの?
EVの充電がなくなってしまった場合、基本的には充電するしかありません。最も一般的な対処法は近くの充電ステーションでバッテリーを充電することです。
しかし、充電ステーションが近くにない場合はレッカーサービスを利用することも考えられます。2020年からJAFは「EV充電サービス」のロードサービスの試験運用を開始しました。
このサービスは、充電機材を搭載したバン型サービスカーが現場まで来て、その場で充電を行ってくれるというもの。EVの場合、押しがけはできないため、このようなサービスは大変便利です。
このサービスは東京、神奈川、愛知、大阪でスタートし、全国への拡大を予定しています。
ほかに動かす方法は?
EVが充電切れになった場合、通常の手段では動かすことは基本的に難しいでしょう。しかし、いくつかの特殊な方法を利用することで一時的に充電し、移動させることも可能です。
ただし、これらの方法は緊急時の一時的な対応であり、常に安全で確実な充電計画を立てることが重要なことは言うまでもありません。一つは多機能ジャンプスターターの使用。一部の多機能ジャンプスターターは、EVのバッテリーに短時間の充電を供給することが可能です。
しかし、EVのバッテリー容量や仕様によっては対応できない場合もあるため、製品の仕様を事前に確認する必要があります。もう一つが、ほかのEVやPHEVからの充電を受け取ること。
この方法では、専用のケーブルやアダプターが必要となりますが、短距離の移動に必要な電力を補充することができます。
繰り返しになりますが、これらの方法はあくまで一時的な対処法であり、充電インフラの整備状況や充電計画の重要性を十分に理解しておくことが重要です。
EVを安全に、そして効果的に利用するためには、事前の充電計画や充電ステーションの位置を確認し、適切な充電方法を選択することが求められます。
課題3:充電時間の長さ
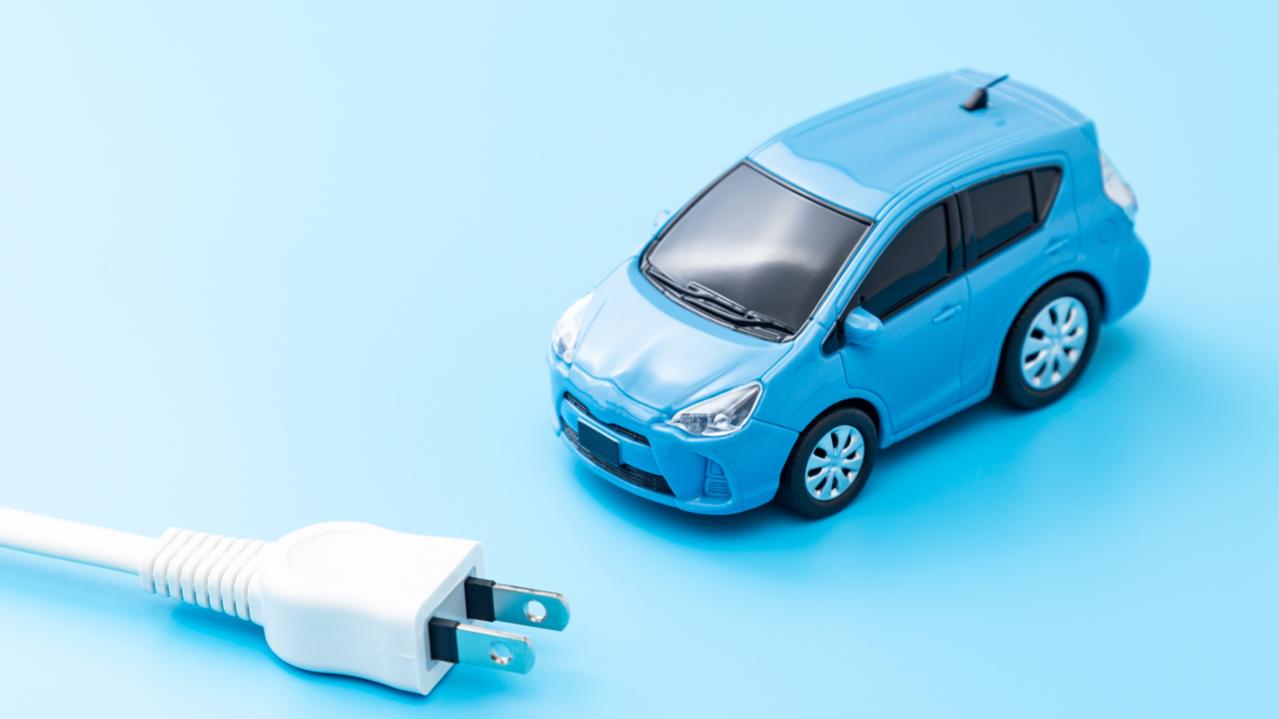
EVが電力切れの状態になった場合の充電時間は、使用する充電器のタイプによって大きく異なります。急速充電器は普通充電器と比較すると迅速な充電が可能ですが、それでもガソリン車と比較すると非常に多くの時間を必要とします。
普通充電器を使用する場合は充電にさらに長い時間がかかるため、日常の使用では充電計画をしっかり立てておきたいところです。以下は、日産リーフなどの代表的なEVの場合の充電時間の目安としてお考えください。
急速充電器の使用時
普通充電器の10倍を超える速さで充電することも可能な急速充電器ですが、バッテリー残量警告灯が点灯した時点からの充電開始で約60分かかるとされています。
急速充電器は、カーディーラーや高速道路のサービスエリアなどに設置されています。道の駅やコンビニに設置されている急速充電器は20~30kW程度しか出力できないタイプが多いですが、90kW以上の高出力タイプも提供されています。
家庭用の普通充電器の使用時
普通充電器は家庭での使用に適していますが、フル充電までの時間は長くなります。
充電器の種類により異なりますが、3kWタイプの普通充電器ではバッテリー残量警告灯が点灯した時点からフル充電まで約23.5時間、6kWタイプの場合は約12.5時間が必要と言われています。
EVの普及に向けてこれから求められること

EVの普及に向けては、これまで触れた内容以外にも多くの課題が存在しています。その中から複数の課題をご紹介します。
インフラの整備
日本でのEVインフラ整備においては、いくつかの重要な課題が存在しています。
まず、既存の充電器の新設や、急速充電器の設置など、充電ステーションの拡充が急務となっています。さらに、充電インフラの利便性の向上も大きな課題です。ユーザーが容易にアクセスできる充電ステーションの整備や、充電の待ち時間の短縮などが求められています。
設置やメンテナンスに発生する費用
EV用充電器の費用も重要な要素です。特に初期投資や継続的なメンテナンス費用の発生はEVの購入をためらわせる要因になってしまう可能性があります。
家庭用EV充電器の設置に関しては、費用は大体10万円から30万円の範囲で変動します。この費用は設置場所までの距離や配線の長さによって異なります。
つまり、設置場所や状況によっては、費用が予想以上に高くなることもあり得るのです。
一方で、急速充電器の年間メンテナンス費用はおよそ30万円となっており、個人が導入するにはやや高額です。ただし、メーカーや契約の内容によって費用は異なるため、一概には言えません。
また、普通充電器では基本的にメンテナンス契約は必要ないため、これらの費用はかからないというのが一般的です。
保険料
EVの保険料は、一般的にガソリン車やディーゼル車よりも高めに設定されています。
保険料は車種やグレード、運転者の年齢や過去の事故歴などによって異なりますが、EVはガソリン車に比べて車両価格が高い傾向にあります。その結果として保険料も高くなってしまうこともあるのです。
海外のデータですが、英国保険会社協会によればEVの保険金請求額はほかのエンジン車に比べて約25.5%高く、修理にかかる期間も14%長いとされています。
オンラインの保険比較サイト「ポリシージーニアス」のデータによると、2023年のEVの月払い保険料は平均で206ドルで、化石燃料車に比べて約27%高いことがわかります。
さらに、金融比較サービス「Confused.com」は、2022年に比べてEVの保険料が72%増加したと報告しています。日本の保険会社には、エコカーに適用される割引サービスを提供している会社も。
契約時には、エコカー割引の取り扱いの有無を確認の上、対象車種や割引率なども確認しておくことをおすすめします。

カースモーラちゃんのまとめ
車両そのものの価格、保険、充電機に関するようなお金の問題はもちろん、国としてのインフラ整備もまだまだ改善する必要があるみたい。今後のEV普及に向けて、どんな変化があるのか注目だね。
こちらもオススメ
こちらもオススメ





