NEW

軽商用EV ASF2.0(画像は公式サイトより)
軽商用EVバン「ASF2.0」佐川急便との共同開発。「配送ドライバーの声を反映」した快適な車体設計が話題。‐ASF株式会社
公開日:2024/06/07更新日:2024/05/30
TEXT&PHOTO 石原健児
目次
EV時代を予感、商用利用を目指し創業
「これからはEVを店頭販売できる時代がくるのでは?」ASF株式会社、代表取締役社長の飯塚 裕恭氏はヤマダ電機の副社長を務めていた頃、EVに興味を持った。しかし、事業化が難しいと感じた飯塚氏は、ヤマダ電機を退社。以前から関係があり、EV調達に意欲的だった佐川急便からの相談を機に、EV製造の共同開発を進めるべく、2020年にEV開発のベンチャー企業ASF株式会社を立ち上げた。
佐川急便という運送業界のトップ企業をパートナーとしたため、商用車向けEVというコンセプトは最初から固まっていた。具体的な用途は「ラストワンマイル」と呼ばれるエンドユーザーに届ける配送業務である。ただし、EVを製造するには幾つかの選択肢がある。国内の既存EV車種を活用するか、海外メーカーのEVをカスタマイズするのか…。
軽商用EVに最適な車体を求め、自社で企画・開発へ

ASF株式会社 事業企画部副部長の村上 多加夫氏
悩んだ末ASFは、車両コンセプトを自社で考え、生産は外部に委託する「ファブレスメーカー」として開発をスタートした。
「設立当初から創業メンバーは海外メーカーをまわり、当社の要望に応えてくれる委託先を探していました。」事業企画部副部長の村上氏は当時を振り返る。開発をスタートした時、国産車の軽バンEVは1車種だけであった。佐川急便などラストワンマイル系の配送業務を行っている業種が使用することを想定すると、当時は一充電での走行距離(バッテリー容量)が十分ではなく、業務中に充電をしなければならない可能性があった。
「軽自動車は日本独自の規格ですので、海外メーカーの車種を持ってくるのも現実的ではありませんでした。」と語るのは、CTO・車両開発部部長の山下氏。「創業時から、国内でEVマーケットを確立したいという目標を持っていました。ユーザーが安心できるよう、日本の軽規格に合わせた車を自分達で作ろうと考えたんです。ですから、海外車のカスタマイズと選択という選択は考えられませんでした。」(村上氏)
そんななか、佐川急便側からのオーダーは、「途中充電不要で配送業務に耐えうるEVを作ってほしい」という内容だった。どうせ一から作るのであれば、積載量や使い勝手も考慮にいれ車両をデザインしたい。そこで、ユーザーである佐川急便のドライバーへ大規模なアンケートを実施し、開発車両に求める点をヒアリングした。全国から集まったアンケート用紙は7200枚に及んだ。
ドライバーの声を十二分に反映した車体設計
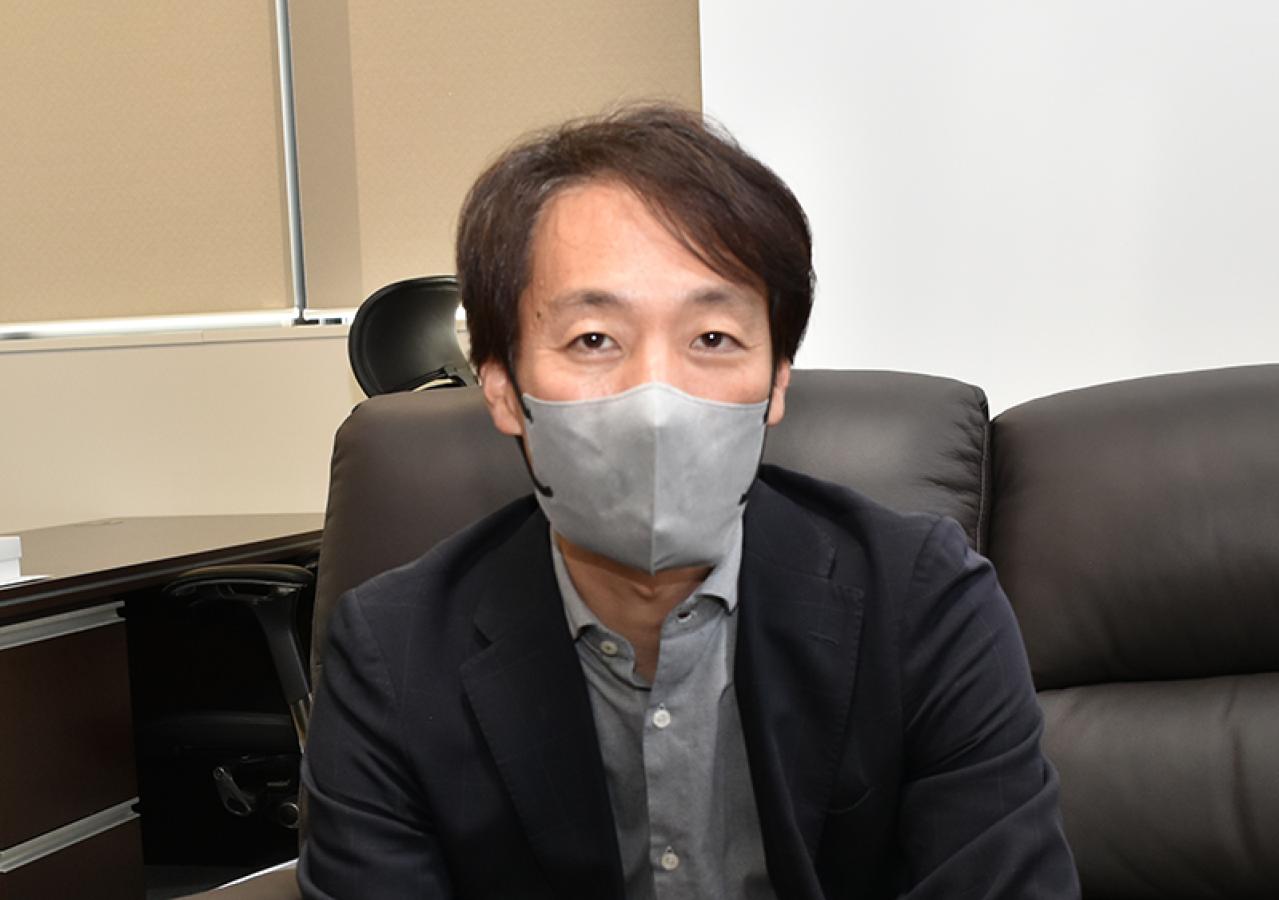
ASF株式会社 CTO・車両開発部部長の山下 淳氏
アンケートで寄せられたのは、現場でなければ考え付かない貴重なアイデアばかりだった。「夜間に荷物の確認作業がしづらいので荷室のライトをもっと明るくできないでしょうか」「ドリンクホルダーに紙パックがはいるといいな」「車の中はお弁当がたべづらい」「業務時、車の中ではパソコンを膝の上で広げています」「書類ファイルの置き場に困っています」回答は車の使い勝手だけではなく、実務上の悩みから休憩時の快適性まで幅広い分野に及んだ。配送業にとり、車は日中の大部分を過ごす相棒のような存在なのだ。開発スタッフはその重要性を再認識した。寄せられた声を反映し、ドライバーのニーズにマッチするクルマを目指し開発は進んだ。
ほどなくして、寄せられた声は一台の軽バンEVとして形となった。開発から完成までに要した時間はわずか3年。「ASF2.0」の誕生だ。ボディサイズは全長3395×全幅1475×全高1950mm、荷室サイズは長さ1690×幅1340×高さ1230mm、最大積載量は350kgと国内の軽自動車基準に準拠。荷室の床はフルフラットで荷物が積みやすい仕様となっている。ダンボール小(幅497×奥行315×高さ293mm)で45箱、ダンボール大(幅601×奥行450×高さ453mm)で14箱が積載でき、一般的なガソリン車の軽ワゴンと比べても積載量に遜色はない。走行距離はフル充電で243kmと、こちらも一日の使用に十分耐える。夜間に充電し、日中の配送業務に備える、という使い方を想定している。

飲み物やファイルなどの収納スペースも充実(画像は公式サイトより)
ASF2.0には、ドライバーへの配慮が随所にちりばめられた。運転席は、助手席よりもシート幅を広く設計した。食事やパソコン作業が快適に行えるように、ステアリングには脱着式のテーブルを装備。シート横にはファイル収納用のスペースを設けた。紙パック飲料の収納スペースも完備している。「フルフラットの荷室の下には、小物が入れられる引き出しと、台車の収納スペースを設けました」(村上氏)。EV車の特性を生かし、スマホの充電や給電用のコンセント、専用タブレットも備えており、運送業者には至れり尽くせりの設備だ。また、衝突被害軽減ブレーキなど各種安全装備も完備。例えば、ASFオリジナルの「自走事故防止システム」は、ドライバーがDレンジで降車するとシフトが自動的にPに切り替わる。
ASF2.0はユーザー企業への提供を既に始めており、2024年3月の時点で佐川急便のほか、マツキヨココカラ&カンパニーなど複数の企業に納入を進めている。
ニッチな分野でユーザー目線のEV車両を提供

運転席には脱着式のテーブルを装備(画像は公式サイトより)
今後、国内大手自動車メーカーを筆頭に、EV市場は群雄割拠の様相を呈するのではないか?プロモーションで勝算はあるのだろうか?老婆心ながら、事業企画部の村上氏に聞いてみた。
「当社が注力する軽規格の商用EV車の市場規模は約40万台です。対して、日本国内の自動車市場は数百万台規模。B2B向けに特化した車を投入し、生産・販売・プロモーションなどのリソースをつぎ込んでいくのは、経営サイドからみると判断がつかないと思います。」ニッチな市場、加えて、ASFは自社工場を持たないファブレス企業。コストの面でも十分に勝機がある。「ニッチな市場にお客様のご意向に沿ったものを創り上げ、お届けしていく、弊社ではそうしたユーザーファーストの視点にこだわっています。」村上氏は、力強く答えてくれた。
製造先の選定は「コスト・納期・意欲」を重視
ASF2.0の製造を手がけるのは、中国の「柳州五菱新能源汽车有限公司」。广西汽车集团有限公司のグループ会社として2021年6月に設立され、EVはもとより、SUV、バン、トラックなど年間100万台以上を販売している。ASFでは、代表と副代表が海外へ赴き、複数の企業と交渉。柳州五菱新能源汽车有限公司を製造パートナーとして選んだ。
「製造先の選定基準は『弊社が求める納期とコストに対応できるか』という点です。」と村上氏。日本の車両規格を理解して、ともに一から創り上げてくれるか、モノづくりへの意欲も重視した。
オリジナル商用EVをわずか3年で完成

ASF2.0のモックアップ(画像は公式サイトより)
アウトソーシング先は海外企業。オンラインだけでは、意図が十分に伝わらないことも多く、モックアップ(製品設計や商品企画の段階で試作する模型)の制作だけでも何度も現地へ足を運んだ。また、物理的な距離だけではなく、モノづくりの基本的な考え方の違いにも苦労した。山下氏も村上氏も中国スタッフに時折みられる「問題があれば修正すればいい」という考えが気になった。
一例として挙げてくれたのが、ドアの製造に関するやり取りだ。現地スタッフは貨物車のドアは堅くても開け閉めできればよい、といった認識を持っていた。しかし、日本ではその基準では商品として成り立たない。よくよく話を聞いてみると、中国ではドアを手荒く開け閉めするドライバーを見かけることも少なくないという。「決していい加減なものを作るということではありませんでした。要は文化や習慣による考え方の違いです。」(山下氏)
とはいえ、考え方のギャップは一朝一夕には埋まらない。山下氏や日本側スタッフは、現地スタッフと何度も話し合いを重ね、要求する品質レベルの共通認識を築き上げた。日中どちらのスタッフも良いものを作りたい、というゴールは同じ。最初から完璧を目指す日本側のスタッフとは、完成までの道のりが違うということだ。「改善点のフィードバックを理解した後は、迅速に対応してくれました。試作車を作ってから量産までの期間はわずか半年です。おかげで商用EVの企画から量産まで、3年ほどで完成にこぎつけました。」(山下氏)
リース方式で車両を提供、運行データの活用も
ASF2.0は販売ではなくリース方式で車両を提供している。車両販売を担う企業のひとつはコスモ石油マーケティング株式会社。これまでコスモ石油が築き上げたカーリース事業のノウハウを生かし、バッテリー保証やメンテナンスなども提供する。全国に点在するスタンドは、気軽な相談先として心強い。ユーザーは、環境負荷軽減のため、コスモ石油が提供するグリーン電力の利用も選択できる。ASF株式会社では、コスモ石油以外の企業でもASF2.0の取り扱いができるよう販売チャネルを拡大している。
ASFがリース方式を選んだ大きな理由はバッテリーの再活用だ。「EVの課題の一つがバッテリーの再活用です。リース契約にすることでバッテリーの管理が可能になります。現在リースしている車両のバッテリー交換は約6年後。消耗状態なども見ながら、バッテリーのリユースなど活用方法を模索したいと考えています」。(村上氏)
ASFがユーザー企業に提供しているサービスがもう一つある。走行を通じて取得した車両データの活用だ。ドライバーの承諾を得た上で「速度、位置情報、ブレーキ・アクセルの使用状況、バッテリー残量」などの車両データを取得。「ダッシュボード機能」というデータ提供サービスで、ユーザー企業に車両の運行状況やバッテリー残量を提供している。企業からは車両管理に役立つと好評を博しており、今後もさまざまなデータの活用・提供を想定している。
国内外の認証を取得、個人ユースや海外進出も視野に
2023年、ASF2.0はPHP(国内の輸入車認証:国土交通省)、WVTA(欧州車両型式認証)と国内外の認証を取得した。PHPの取得は国内の販売、WVTAの取得は今後EU各国や東南アジアでの販売に役立つ。「まずは国内市場の基盤づくりに注力しますが、今後は海外への進出も視野に入れています」村上氏は今後の展望を語った。
ASFはこれまで、「Japan Mobility Show 2023」をはじめ日本自動車輸入組合(JAIA)主催の輸入車試乗会などいくつかの展示会や試乗会に出展してきた。来場者からは「価格は?」「走行距離は?」といった質問を受けることも多く、ASF2.0のリースに関して個人からの問い合わせも少なくない。最近では、さまざまな業界から商用EV車両への問い合わせも増え、EVの持つ可能性を感じている。
地球と人に優しい乗り物づくり

荷室はフルフラット、ドライバーへの配慮が随所にみられる(画像は公式サイトより)
ドライバーの声から生まれたASFの軽商用EV。「静かに走り出せる」「ギアチェンジの揺れがないので、荷崩れが減った」利用したドライバーからはこうした声が寄せられている。アクセルワークへのスムーズなレスポンス、エンジンの振動が少ないなど、ガソリン車と比べ静粛性が高いのがEVの特徴の一つ。「1日中運転する場合、疲労度の蓄積が全く違うと思いますよ」物流のラストワンマイルを担うドライバーたちには、ぜひ体験して欲しいと山下氏は語る。
独自のEVを一から作り上げたASF。バッテリーのリユース、再生エネルギーの活用など、今後挑むのは持続可能なエネルギーシステムの構築だ。日本の街をよりクリーンに、ドライバーに優しい環境を。ASFの更なる挑戦に期待したい。



